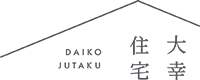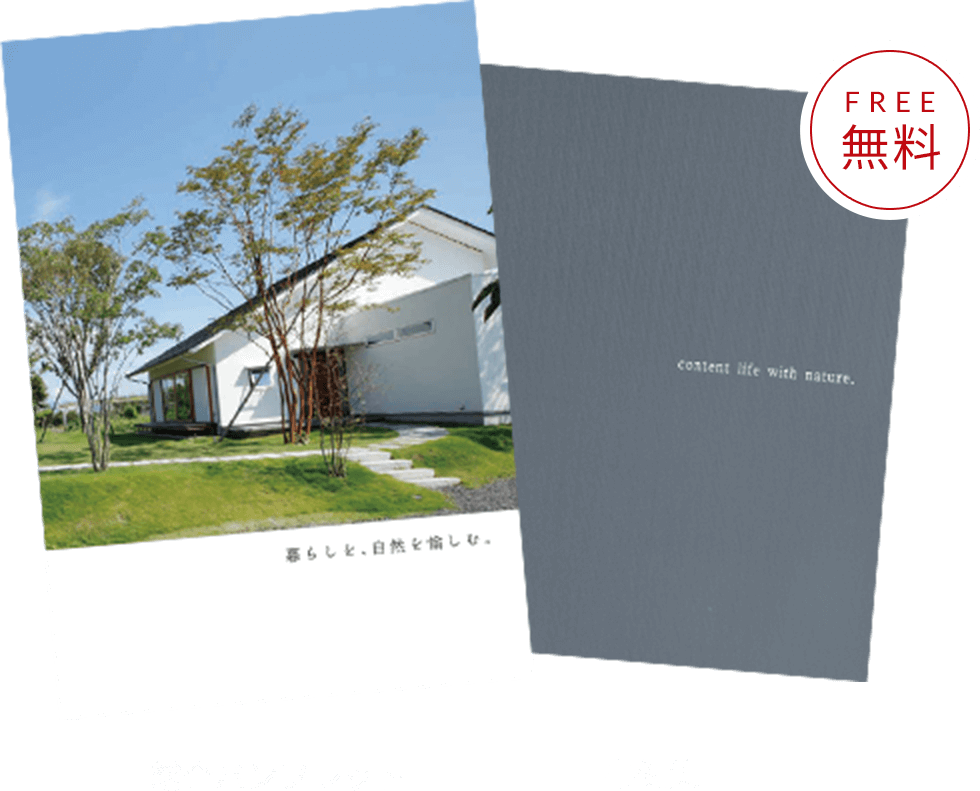代表インタビュー
「何でもやれる」から「やらないことをつくる」へ

可児工房に入社した当時はどんな会社でしたか。
当時可児工房で働いていたのは、4人ぐらいでしょうか。年上の人がほとんどで、よくある地場の工務店みたいな感じでした。「何でもやりますよ」というスタンスで、木造もやれば鉄骨もやるし、木造なら軸組もやればツーバイフォーもやる。建物のデザインにしても、和風から洋風まで、何でもやりました。「お客さんの希望を実現します、夢を叶えます」みたいな言葉で、何でもお客様に言われたようにつくるのが、その頃の売りでしたね。
代表に就任されてからは、どのように取り組まれてきたのでしょうか。
今後の方向性を考えようと、改めて自分の会社を見つめたときに、「ここが光っている」という強みや特徴が出てこなかったんです。それまでは強みだと思っていた「何でもやれる」ことが、お客様からすると「何もやれない」と捉えられてもおかしくないのではと、そのときに初めて感じました。そこで、「もっとやるべきことを決めよう」「やらないことをつくっていこう」と決めたんです。
具体的には、どんなことですか。
まず決めたのが、「一つの工法のみにしよう」。それまではお客様のコスト等に合わせて、どんな工法にも対応していました。その状況に、すごく自分の中でジレンマというか、腑に落ちないところがあって。やっぱり自分たちが信じてやれるものを、何か一つつくりたいと思い、木造軸組工法に絞ってしまおうと決めました。
二つ目は、すべての構造材を、地元・岐阜県産の性能表示材に切り替えること。流通量が多くてコストも安い輸入材が多く使われる中で、地元産木材は消費量が上がらず、山も荒れていってしまう。それなら、地元の工務店が使っていくしかないんじゃないかと思ったんです。岐阜県産木材の中でも、品質・性能が担保された「性能表示材」を使おうと決めました。地元の山を守るだけでなく、輸送の際のエネルギー消費量や CO2 排出量を抑えられる。地産地消は、私たちができる一番良い形だと思います。
三つ目は、工務店における建物の性能の評価基準は曖昧であるため、評価制度によって住宅性能が明確になる長期優良住宅は、これからの住宅業界において、最低限担保すべき品質であると考えています。特に、耐震性能は住む方お客様の命に直結する重要な要素です。そのため、最高ランクの「3」の取得を標準とするとともに、最も安全性が高いとされる許容応力度計算(構造計算)を一棟ずつ実施しています。「お客様の希望があれば行う」のではなく、すべてのお客様に安心していただけるよう、高い安全基準を標準としました。
デザイン性と快適性を両立する家づくり

家づくりで大事にしていることは何ですか。
デザインにおいては、センスや気の遣い方が大事だと思っています。私は、デザインに関しては、コストがかかるとは思っていません。例えば、窓を一つ付けるにしても、どの位置に付けるかによって、美しく見えたり、外の景色が綺麗に抜かれたりします。同じ窓1本の値段でも、どこにどう付けるかということだけで、建物自体の品質が変わってくるんです。そういった感性を研ぎ澄まして、「なんか綺麗だな」「雰囲気がいいね」と感じてもらえるような建物をつくっていきたいと考えています。
また、デザインと住み心地の良さが共存できる家づくりを目指しています。日本、特に岐阜県は高温多湿で、冬寒くて夏暑く、台風が通過することも少なくありません。今は軒がない家が増えていますが、昔の家には深い軒があって、建物を風雨から守り、夏場の日差しを抑えながら、窓からは涼しい空気を取り入れていました。そういった昔ながらの日本家屋の良さを大事にしたいと思い、つくる建物も、基本的には軒を深くしているんです。そこに少し今らしいデザインも取り入れて、景観としての美しさにも配慮しています。
快適性を求めるなら、昔ながらの日本家屋じゃなくても、ハイテク・デジタル等の手法もあると思いますが。
例えば、断熱性を上げたり窓を小さくしたりして、そこにエアコンを入れれば、快適さは得られると思います。ただそこには、建築としての力量は問われないですよね。そのような手法を否定するつもりはまったくないのですが、「もっと建築でやれることは建築でやろうよ」と思うんです。もちろん、少しでもエアコンの効きが良くなるようにすることも大切なのですが、それがなくても、ある程度の心地よさは得られるようにしていきたい。それは、建築的な工夫や考え方によって構築されるもので、まさに私たちの腕の見せ所なわけです。私たちの存在意義はそこにあって、そうでなければ、どこにでも均一な建物を建てていれば良い話ですよね。建築はデザインと快適性、そしてその土地の気候風土を考えながらつくるところが面白みでもあるし、これまでに積み上げてきた経験が活かせる場でもある。そういう部分を大事にしたいと思っています。
さまざまな部分にこだわると、コストもかかるのではないでしょうか。
すべてにおいてコストを優先してしまうと、私たちの考えや取り組みは実現できないと思うんです。
お客様から頂いたお金は、最終的には僕たちに委ねられます。どこの材木屋さんで木材を買うのか、どの職人さんに頼むのかというのは、お客様の大切なお金をどう使っていくかということになります。その中で、地元の工務店としてできることは、地域にお金を循環していくことだと考えました。地元の山で木材を採り、そこに関わる人たちや、地元の職人さんに仕事を依頼してお支払いする。そうやって、お客様が家を建てるためのお金が地域を循環していくことは、結果的にお客様が暮らしていく場所をつくることにもつながっていくと思うんです。単純にコストとして捉えると高いかもしれませんが、そんな背景を考えれば決して無駄な費用ではないと思いますし、それをやるのが僕たちのような工務店のあり方なのかなと思います。
日本人が元々持つ美意識を大切にする

大幸住宅の家は和風の建物が多いようにみえますが・・・
私は和風であるとはあまり感じていません。先ほどもお話ししましたが、弊社がつくる家は、基本的に軒を深く出すことが多いんです。一番の目的は、太陽高度が高くなる夏場の日射の侵入を抑えること。四方に深く出してるのは、外壁に当たる雨水の量が少なくなり、表面の劣化を抑えられるためです。窓と周りの開口部から侵入してくるリスクも減らせます。
もう一つは、見た目的な部分。これはちょっと日本的なデザインの感覚になってしまうかもしれませんが、軒が深く重心が低い落ち着いた佇まいっていうのが、やっぱり私は綺麗だなって思うんですよね。
日本的なデザインの感覚ですか。もう少し詳しく教えてください。
家づくりを長くやってきて改めて思ったのは、私たちのつくった建物は、5年10年でなくなるものではなくて、20年30年とずっと先まで形に残り、その地域にあり続けるものだということです。もし流行りのデザインでつくったとしたら、今は良くても、30年後に見たときにどうなのか。その視点で考えると、今まで残っている建物には必然性があって、それを見て育ってきた自分たちの中には、美しさを感じられる感覚が少なからずあると思うんです。例えば、洋風の家が好きな人でも、京都の古い町並みには何となく惹かれる。日本人として昔から刷り込まれた、普遍的なものなんだろうと思います。そういった要素がある家の方が、長い間そこに残るものとしては、やっぱり美しいんじゃないかなと思うんですよね。
ただ、そこに建つ家は僕たちがつくれても、隣の家までは関与できません。いくら自分たちが軒を深くした町の佇まいに合う家をつくったとしても、全く系統が違う建物が建ち並べば、統一感がないですよね。それでも30年40年と残り、子どもたちの原風景になっていく。そう考えたときに、隣合う家とのつながりまで含めた、町並みづくりにもチャレンジしてみたいと思い立ちました。そこで、御嵩町上恵土にある7区画の分譲地※をすべて購入し、一から町並みを形成するという、試験的な取り組みを始めたんです。
はじめての町並みづくりへ

それはどのようなものでしょうか。
そこでは、建物の外から見た町並みを整えるために、ゆるめのルールを2つ設けました。まず一つ目は、外観です。御嵩町は古い宿場町ということもあり、その面影を残したいと思ったんです。そこで、「黒い板張りの板をどこかに使うこと」「それ以外の壁は左官屋さんの手仕事による塗り壁にすること」「格子など、ポイントとなるような木部のアクセントを入れること」を共通ルールとしました。もう一つは、隣地との間に塀などは設けず、ほぼフラットな状態でつなげること。区画全体で一つの庭のようにつくることで、境界線を曖昧にして、つながりを強く持たせました。植栽にはアオダモの木のほか、お隣さんにお裾分けできるような、実のなる木も植えました。
実際にやってみてどうでしたか。
ルールをつくったことで、思った通りの町並みをデザインできただけでなく、もう一つ良かったことがあったんです。この区画に入居してくださった方は、窮屈と思われそうなルールにも寛容で、優しくておおらかな人ばかりで、私の考えにも共感してくださる方が多くて。だから、近隣との関係性やコミュニティも、すごくうまく築かれている感じでした。ふつうであれば、私たちができるのはあくまで家を建てることだけで、住んでいくのはお客様たちですよね。なので今回、周りの人まで含めた良い環境を提供できて、本当にやってよかったなと思いました。
また新たに7区画※増やす予定ですが、これからもこんな輪を広げていきたいなと思っています。最終的な理想は、白川郷のようなコミュニティ。茅葺き屋根の葺き替えを皆で手伝うように、黒い板張りの板の塗装を皆でやる。協力し合っていくことで、メンテナンスコストが抑えられるだけでなく、「自分のとこをやってもらったから、今度はあなたのとこも手伝うね」みたいな、お互い様の感覚も芽生えると思うんです。そんな薄れつつある感覚を、もう一度コミュニティの中でつくってみたいなと思っています。
※2025年現在は19区画になりました
目に見えない部分にこそこだわる

大幸住宅はどんな会社ですか。
真面目な会社だと思います。スタッフも、職人さんも、会社のあり方自体もそうかもしれないんですが、あまり仕事をお金儲けの目線で捉えてないと思うんです。家を建てることが純粋に好きであったり、お客様と接することが好きであったり。家づくりを通した仕事に対して、真面目に向き合っている人が多い印象がありますね。だから、お客様との間で何かあったときは、お客様の考えを優先する。手直しがあったときは、コストがかかったとしても、最終的にお客様が納得してくださるかどうかを大事にする。あまり、儲かる会社ではないですよね(笑)。
お客様の目に見えないような所まで真面目にやるのは、損ではないですか。
そうですね。もっとアピールしてほしいです。営業スタッフにも「こんなところを一生懸命つくってるんです」とか。現場スタッフは、本当に見えないところにも、こだわってやってくれているので。それがもっとお客さんに伝わってほしいですね。ただそれは、自分たちにとっては当たり前にやっていることだよね、と思うところもあって。
私自身は、自分たちのつくる建物を決して高いとは思っていないんです。そういう必要なところにきちんとコストをかけていれば、どうしてもこれぐらいの費用はかかってしまうんですよね。お金儲けを考えたら、本当はもっとかかると思います。逆に、「どうしてこんなに安く出してるの」って思っています(笑)。
目に見えないこだわりについて、詳しく教えていただけますか。
構造的な安全性や、雨水の侵入を防止する部分のような、後で触れないところは、施工時にやっておかないといけないですよね。私が仕事を始めた頃は、基本的に大工さんや現場監督任せで、その辺のルールがなかったんです。例えば、10年後にメンテナンスに行こうと思っても、どんなふうにつくってあるのかがわからない。当時の大工さんや現場監督が引退したら、もう本当にわからなくなるんです。これでは駄目だと思い、そういった部分を明確にしてマニュアルに起こし、それを見れば大工さんでも新人の現場監督でも指示が出せるようにしました。
あとはそれを、きちんとチェックできる体制づくり。社内でのチェックはもちろんですけど、瑕疵保険の検査とは別に、第三者の検査機関も入れて、見えなくなってしまう部分にすべて検査に通します。昔はお客様が自分で検査会社に依頼することもあったのですが、自分たちのつくるものの品質をしっかりと担保するために、見落としなくチェックしたいという想いで行っているんです。そういったところにも費用はかけていますね。
現場で見てもわかりにくいものでしょうか。
パッと見てもわからないですね。基礎の中の配筋なら、コンクリートを打ってしまったら見えないですし。上に建物を建てたら、余計に見えないですしね。そんなところに、じつはコストがかかっています。しかし、お客様の目がいくのは、表面的なデザインや使っている材料などの目に見える部分。そういった部分を評価いただいて、お客様が選んでくださることが多いんですが、本当のこだわりはもっと見えないところにあるんです。20年後30年後でも、「あのときこんな仕事をしてて良かったね」と思ってもらえるようなところに、手間や費用をかけていることを、皆さんに知っていただきたい。そのアピールがまだできてないことが、残念ですね。
住まう人が愛着を持てる家を、1つでも多くつくりたい

社長にとって、家づくりとは何でしょうか。
人生(笑)。それは言い過ぎかもしれませんが、実際ほとんど休みなく働いています。でもまったく、苦じゃなくて。半分趣味みたいなところもあって、仕事していた方が体調も良くて。やっててやっぱり楽しいんですよね。お客様にとっては、基本的に一生に一度建てられるかどうか。それに対して僕たちがお答えできるのは、その1回しかないわけです。そこに全力を注いでいくっていうことは、他ではなかなか得られないような仕事のあり方だなって思っていて、すごくやりがいを感じます。だから全然、自分の時間が欲しいとは思わないんです。人生は大げさだったかもしれないですが、それに近いようなところはありますね。もう一度生まれ変わっても、この仕事をやりたいなとは思っています。
住まう人にとって、家はどういうものであってほしいと思いますか。
私たちがつくるものは、既製品をはめていくというより、一つ一つ手作りしていく要素が多いんです。材料に関しても、無垢材を使っています。時間とともに変化したり、予想していなかった動きをしたり。建てたときも建てた後も、手はかかると思うんですよ。そういう部分と上手に向き合い、楽しみながら、家の手入れをしていけるような住まい方があると良いなと思っています。だんだん古びていって、ローンを払った頃に「もう使い古したね」と言われるような家ではなくて。住みながら手をかけることで愛着が湧いて、20年後30年後でも「この家で良かったね」と思えるような家であってほしいと思います。
そのために、私たちもできる限りバックアップしていきたいと思い、最近ではメンテナンスのワークショップなども始めました。前回は植栽の手入れをしましたし、今度は木部の塗装、その次は床や室内の木の手入れをやろうと思っています。やり方がわかれば簡単にできることや、メンテナンスや手入れの楽しさを知っていただき、少しでも家に愛着を持ってもらうための手助けになれば嬉しいです。
季節を感じられる家を目指しているのでしょうか。
私たちのつくる家は、大きな開口部を設けることが多いんですよね。たまに、木製の大きな1枚の窓をつくって、それを壁の中に引き込むこともあります。木製窓を使う理由は、見た目的な良さもありますが、アルミ窓や樹脂窓ではできないような、大きな窓を引き込む開き方ができるからなんです。そうすると、中と外のつながりが生まれ、自然な心地よさが得られる。そういう、庭も含めて一体となった空間を持つ建物にしたいと思っています。そのために、木製窓の先にはデッキやテラスをつくって、その向こうに植栽を植えるんです。5月ぐらいには芽が出て、新緑が見える。夏を越えて秋には、またその葉の色が変わってきて、もうすぐ冬が来るなと感じる。冬になれば、家の中で薪ストーブを焚ける楽しみがやってくる。そんなふうに、毎年四季を通して楽しめる家づくりができると良いなと思います。
これからどんな会社にしたいですか。展望があれば教えてください。
これから世の中に建つ家を、全部自分達で建てられれば、町並みが整って綺麗になるような気はします。そうもいきませんが(笑)。しかし、私たちはそれくらいの想いを持って家づくりをしています。自分たちが1つでも多く建物を提供することができれば、少なからず町並みは良くなっていくと思いますし、お客様は快適な生活を得ることができる。通行人も、外から植栽を見て楽しむことができると思います。だから、少しでもつくれる家の数を増やしていきたいという気持ちは念頭にありますね。そのためにも、可児以外の場所でも家づくりのお手伝いができるようにしていきたいと考えています。例えば、岐阜の西の方や愛知県の方にも、家づくりの拠点となる場所をつくって、地元の職人さんたちにお仕事をしてもらって。自分たちの仕事を通じて地域に還元していくという良い循環を、いろんなところに広げていきたいなと思っています。
そのために、新しいスタッフさんもたくさん入ってほしいですし、お客様にも弊社の良さを知っていただいて、「大幸住宅で建てたいな」と思う人が1人でも増えれば嬉しいです。